×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
V派の総帥、S-OK元帥の講演会ではT氏も末席を汚し、
風人社さんのサイト
http://www.fujinsha.co.jp/kazesayage/kazemtid.html
にはT氏の頭頂部が掲載されてます(禿藁)。
M-Kご老公の呼びかけに「いざ鎌倉」、「いざ丹沢」、いや
「いざ平塚」と出陣したが、会場はV派の大将が総出で
アセった、隅っこで小さくなるしかなかったとT氏は申します。
んで講演後に八十ン歳のおじいちゃんがおもむろに立ち上り、
「報国造林」とかワケのわからんことを口走って会場をして
狼狽せしめたが、早速おじいちゃんを捕獲して「報国寮」の
件につき尋問すると、これが知らぬ存ぜぬの一点張りで
T氏をして落胆せしめたそうです。
"報国造林"でググると、神奈川県は「報国造林奨励規程」を
昭和14年につくっており、要するに補助金を出して青年団や
中学校に植林の労働奉仕をさせた事業っぽいです:
http://www.yurindo.co.jp/yurin/back/393_3.html
「学校林」の制度は明治の初期からあって、T氏は青根小の
1950年物を目撃していますが
 相模原市立
相模原市立
青根小学校の
学校林表示杭
この戦前・戦中期には皇紀二千六百年記念事業としても大いに
奨励され、目を海外に転ずれば、伊・独でも進められたそうです:
http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/handle/2261/22571
風人社さんのサイト
http://www.fujinsha.co.jp/kazesayage/kazemtid.html
にはT氏の頭頂部が掲載されてます(禿藁)。
M-Kご老公の呼びかけに「いざ鎌倉」、「いざ丹沢」、いや
「いざ平塚」と出陣したが、会場はV派の大将が総出で
アセった、隅っこで小さくなるしかなかったとT氏は申します。
んで講演後に八十ン歳のおじいちゃんがおもむろに立ち上り、
「報国造林」とかワケのわからんことを口走って会場をして
狼狽せしめたが、早速おじいちゃんを捕獲して「報国寮」の
件につき尋問すると、これが知らぬ存ぜぬの一点張りで
T氏をして落胆せしめたそうです。
"報国造林"でググると、神奈川県は「報国造林奨励規程」を
昭和14年につくっており、要するに補助金を出して青年団や
中学校に植林の労働奉仕をさせた事業っぽいです:
http://www.yurindo.co.jp/yurin/back/393_3.html
「学校林」の制度は明治の初期からあって、T氏は青根小の
1950年物を目撃していますが
青根小学校の
学校林表示杭
この戦前・戦中期には皇紀二千六百年記念事業としても大いに
奨励され、目を海外に転ずれば、伊・独でも進められたそうです:
http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/handle/2261/22571
(余談の続き)
丹澤報國寮に続き、昭和13年7月に中学生対象の箱根報國寮が開所
されますが、これに先立つ4月には「国家総動員法」が公布され:
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs13-55.htm
6月には「集団的勤労作業運動実施ニ関スル件」の文部省次官
通牒が出て、若年の学徒にも奉仕作業が奨励されています:
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198101/hpbz198101_2_112.html
中坊には始めは1日単位の神社掃除、道路整備の補助あたりでしたが
だんだんエスカレートして大規模な農作業や軍需工場での集団作業に
至るのは周知の通りです。
農家の手伝いをすれば「お土産」があったでしょうし、工場勤務では
給料が支払われた記録があります。これに対し植林はまあタダ働きで、
横浜三中の学校史を見ると、後に報国造林の杉が売られた際には
卒業生から「生徒の汗の結晶だから収入は同窓会に入れろ」という
声があがったそうです(「横浜三中三高緑高六十年史」p.188)。
という具合に報国にも競合他社がいろいろ出現し、事業主体から見れば
労働力の争奪戦になります。重労働をロハで課しメシも不味い報國寮は
当初の理念「治山と治山教育」のみでは対抗が困難となり、國體や精神
修養を持ち出して(旧制高校生には禅宗の寺に籠もるのが流行ってます)
理論武装していったのではないか、とT氏は憶測します。
さて、
昭和12年秋から終戦まで丹沢の治山奉仕作業を実施した「報国寮」。
その評価は、故和田正洲先生(「にのみやの歴史」第2号(1990.3))
にしても矢野慎一先生(「昭和のくらし研究」No.5(2007.3.))に
しても、当初の理念であった「治山」はどこかに消えて、軍人養成の
修練所に成り下がった、というノリです。しかしT氏はどうも納得が
いかなかったと申します。
V派の諸先輩の追っかけを中断してまで報国寮調べを始めたのは、
今なお残る古き小さき美しき堰堤の成り立ちを探るとともに、報国寮の
経験者が本当に治山そっちのけで軍国の風潮一色に身を染めていた
のか? これを確認したかったっぽい、とT氏は言い訳致します。
んで、資料あさりを続けて「○○中学××年史」などを片っ端からあたった
ところ、参加者の感想はやっぱり人それぞれで、中学(旧制)対象の
「箱根報国寮」では寮生は中学生(旧制)らしく大いに楽しんだ節も
伺えて安心した、とT氏は申します。
繰り返しますが報国寮は軍人養成施設などではなく、万事の大義名分が
「報国」と化した風潮の中で、「國體観念の徹底」を同様に第一義に置く
ことで治山の教育の場を辛うじて保った、というのがT氏の理解っぽいです。
丹澤報國寮の合宿活動の実際を宮澤回想記から探ってみます。
運営の特徴(資料(1)より):
************************************************
①治山をはじめ山林事業と青年の育成訓練を結びつけて実施
②常に寮長はじめ職員が先頭に立って万事をリード
③青年の積極的な自発行動を尊重するよう心掛けた
④大自然の中での若者らしく精一杯に自ら挑むよう配慮
************************************************
V派の末席を汚すアマチュア堰堤観察家としては、①の理念でV派を
何人育てることができたか気になるところです。②は何しろみんな
素人ですから、宮澤先生も当然ながら同行して一々指導されたものと
思われます。③④にもかかわらず日課は厳格、労働は過酷で、余暇に
Vルート開拓なんてことはできなかったっぽいです。
職員構成は「県職員指導員3、事業費指導員1~2、同炊事夫1」
とあります(資料(1))。
宮澤先生は在任中に苦労をともにされた職員の方々のご芳名を
列記して感謝されておられます:
************************************************
川瀬国蔵さん、故大津文雄さん、太田孝司さん、落合保治さん、
古谷竹三さん、成井鼎さん、故石井一作さん、鈴木直さん、
高橋重二さん、故北島良平さん、渡辺郁兵さん、山田温恭さん。
************************************************
対象・人員・期間・回数は18歳以上の男子で1回あたり30名、
10日間、4月から11月のおおむね月2回、実質的な初年度の
昭和13年には年12回実施されています(資料(6))。
日々のスケジュールは資料(1)(5)(6)で内容が少しずつ違います。
季節や対象者によって変えていたのかも知れません。(5)(6)によれば
初日は13時集合、最終日は正午解散でともに作業はありません。
以下、T氏(仮名)が報国寮に参加したつもりごっこをするそうです:
 「丹澤報國寮位置図」
「丹澤報國寮位置図」
(資料(6)賛与利)
これを見ていなかったおかげで
秦野寺山の里山巡りを楽しめた、
とT氏は申します。
しかしこの図では蓑毛と宮ヶ瀬の
間の、たぶん丹澤林道沿いに
あるっぽい、ということぐらいしか
わかりませんねえ。
丹澤報國寮への道
丹澤報國寮開所の昭和12年10月当時、既に蓑毛から宮ヶ瀬の丹沢林道が
開通済みです(昭和10年)。ただし山腹の道ですから崩壊しまくりだった
と思われます。アテにはできません。
当時の観光案内「丹沢山塊」(秦野山岳会編、資料(7))を見ると既に
バス路線もあり、
************************************************
・大秦野から蓑毛まで25銭、ヤビツ峠まで60銭(往復1円)
・大秦野から札掛までハイヤーで4円
・橋本から鳥屋まで60銭
・山北から神縄まで49銭
・伊勢原から大山まで35銭
・厚木から煤ヶ谷まで50銭、宮ヶ瀬まで90銭
************************************************
となっています。
1円=今の5,000円で換算するとかなり高いです。
 昭和10年頃の
昭和10年頃の
秦野自動車(株)の
バスと社員。
(資料(8))
高いけど、
ガイドさん付きなら
乗りますか(笑)
バスも高いですが汽車も高いです。
************************************************
小田急で新宿から厚木まで86銭、大秦野まで1円16銭、渋沢1円23銭。
国鉄だと東京から平塚まで1円、山北まで1円44銭。
************************************************
報国寮開所の3ヶ月前には小田急がこんなことになってます↓
 昭和12年7月水害惨状
昭和12年7月水害惨状
(小田急鉄道の破損)
(資料(5))
酒匂川に限らず本邦の
平野は概して河川の
後背湿地ですから、
日本中至る所こんな感じ。
寮費は県の負担ですが旅費については明記がないので自腹かも。
元気があれば大秦野から半日歩きもアリ、V派的には煤ヶ谷~
物見峠~黒岩~一ノ沢考証林~札掛も考えられますが、昼の集合
遅刻厳禁を考えるとリスキーです。
とすると大秦野から蓑毛までバスで、そこから柏木林道、ヤビツ峠
経由が無難っぽいです。
携帯すべき品として入団者心得((5)(6))に
************************************************
作業服(手袋、地下足袋、巻ゲートルを含む)、寝巻、腹巻、手拭、
石鹸、歯磨、弁当箱、印、雑記帳、鉛筆、鼻紙等
************************************************
とあります。弁当箱はカラではなく初日の昼食は途中のどこかで
各自適宜に取るらしいです。褌を忘れても何とかなったと思われ
ますが酒・煙草・夜食を忘れると悲惨です。
厚木市インターネット博物館の「丹澤報國寮絵葉書」によりますと
現地の全景はこんな感じ↓
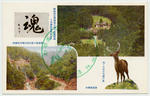
(厚木市郷土資料館の
許可を得て転載)
http://ddbsvr.city.atsugi.kanagawa.jp/museum/post2/L00081.jpg
右上の全景写真は藤熊川を渡った対面の木に登って撮ったっぽいです。
後の建物は高松宮家「有栖川宮記念厚生資金」の援助による講堂で、
開所当時にはまだなかったそうです(4)。
左下は塩水隧道付近のヘアピン付近と思われます。現在は木が茂って
おり、このような展望は得られないそうです。
左上「魂」の「木暮書」は第2代林務課長木暮藤一郎氏と思われます。
木暮氏は「神奈川県林業史」(1)に多くの方々の回想があり、大変な
ヤリ手であって、(予算が潤沢な?)神奈川県の林務課長に東京府
から転ずるためにいろいろ運動したとか他人のアイディアをパクって
特許を取ったとか晩年はよくなかったとか、いろいろ書かれています。
ハンス・シュトルテさんによれば(9)、丹沢林道を諸戸の事務所から
札掛あたりに続く橋に
 「常世」
「常世」
(林務課に常世正俊さんという方が
おられたようです)
 「陣賀」
「陣賀」
 「羽衣」
「羽衣」
 「金時」
「金時」
 「清滝」(笑)
「清滝」(笑)
 「常磐」
「常磐」
 「龍臥」
「龍臥」
と風流な名前をつけたのは、この木暮氏だったそうです。
また大洞隧道と塩水隧道の出入口にも「木暮書」があったそうですが、
大洞は再建され塩水は表札が落ちていて確認できなかった、とT氏は
申します。
T氏は厨房時代にバレーボール部にいたが、靴とかに「魂」と書き
入れることを強制され、アホらしくなってやめたそうです。以来
「魂」と書くヤツにロクなのはいないと確信しているそうです(笑)
(つづく)
【参考資料】
(1)宮澤敏雄「報国寮の回想」「造林史について想う」
神奈川県農政部林務課編「神奈川県林業史」昭和46年(1976)所収
http://www.e-tanzawa.jp/support/e-tanzawa_Supt/info/tanzawa-DB/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%9E%97%E6%A5%AD%E5%8F%B2/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%9E%97%E6%A5%AD%E5%8F%B209.pdf
pp.162~172
(2)神奈川県農政部林務課編「神奈川の林政史」 昭和60年(1985)
第13章「林業教育」
(3)和田正洲「丹沢報國寮」(「にのみやの歴史」第2号(1990.3))
(4)矢野慎一「戦時下・神奈川における報国寮の研究」
(「昭和のくらし研究」No.5(2007.3.))
(5)「丹澤報國寮勤労奉仕施設」(小冊子)昭和十三年三月 神奈川縣
(6)神奈川縣公報 第千百三十四号 昭和十二年九月三日
(7)秦野市史 第5巻「近代資料2」(昭和61年) p.179
(8)「図説秦野の歴史1995」(秦野市発行、1996)
(9)ハンス・シュトルテ「丹沢夜話」(1983)有隣堂
丹澤報國寮に続き、昭和13年7月に中学生対象の箱根報國寮が開所
されますが、これに先立つ4月には「国家総動員法」が公布され:
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs13-55.htm
6月には「集団的勤労作業運動実施ニ関スル件」の文部省次官
通牒が出て、若年の学徒にも奉仕作業が奨励されています:
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198101/hpbz198101_2_112.html
中坊には始めは1日単位の神社掃除、道路整備の補助あたりでしたが
だんだんエスカレートして大規模な農作業や軍需工場での集団作業に
至るのは周知の通りです。
農家の手伝いをすれば「お土産」があったでしょうし、工場勤務では
給料が支払われた記録があります。これに対し植林はまあタダ働きで、
横浜三中の学校史を見ると、後に報国造林の杉が売られた際には
卒業生から「生徒の汗の結晶だから収入は同窓会に入れろ」という
声があがったそうです(「横浜三中三高緑高六十年史」p.188)。
という具合に報国にも競合他社がいろいろ出現し、事業主体から見れば
労働力の争奪戦になります。重労働をロハで課しメシも不味い報國寮は
当初の理念「治山と治山教育」のみでは対抗が困難となり、國體や精神
修養を持ち出して(旧制高校生には禅宗の寺に籠もるのが流行ってます)
理論武装していったのではないか、とT氏は憶測します。
さて、
昭和12年秋から終戦まで丹沢の治山奉仕作業を実施した「報国寮」。
その評価は、故和田正洲先生(「にのみやの歴史」第2号(1990.3))
にしても矢野慎一先生(「昭和のくらし研究」No.5(2007.3.))に
しても、当初の理念であった「治山」はどこかに消えて、軍人養成の
修練所に成り下がった、というノリです。しかしT氏はどうも納得が
いかなかったと申します。
V派の諸先輩の追っかけを中断してまで報国寮調べを始めたのは、
今なお残る古き小さき美しき堰堤の成り立ちを探るとともに、報国寮の
経験者が本当に治山そっちのけで軍国の風潮一色に身を染めていた
のか? これを確認したかったっぽい、とT氏は言い訳致します。
んで、資料あさりを続けて「○○中学××年史」などを片っ端からあたった
ところ、参加者の感想はやっぱり人それぞれで、中学(旧制)対象の
「箱根報国寮」では寮生は中学生(旧制)らしく大いに楽しんだ節も
伺えて安心した、とT氏は申します。
繰り返しますが報国寮は軍人養成施設などではなく、万事の大義名分が
「報国」と化した風潮の中で、「國體観念の徹底」を同様に第一義に置く
ことで治山の教育の場を辛うじて保った、というのがT氏の理解っぽいです。
丹澤報國寮の合宿活動の実際を宮澤回想記から探ってみます。
運営の特徴(資料(1)より):
************************************************
①治山をはじめ山林事業と青年の育成訓練を結びつけて実施
②常に寮長はじめ職員が先頭に立って万事をリード
③青年の積極的な自発行動を尊重するよう心掛けた
④大自然の中での若者らしく精一杯に自ら挑むよう配慮
************************************************
V派の末席を汚すアマチュア堰堤観察家としては、①の理念でV派を
何人育てることができたか気になるところです。②は何しろみんな
素人ですから、宮澤先生も当然ながら同行して一々指導されたものと
思われます。③④にもかかわらず日課は厳格、労働は過酷で、余暇に
Vルート開拓なんてことはできなかったっぽいです。
職員構成は「県職員指導員3、事業費指導員1~2、同炊事夫1」
とあります(資料(1))。
宮澤先生は在任中に苦労をともにされた職員の方々のご芳名を
列記して感謝されておられます:
************************************************
川瀬国蔵さん、故大津文雄さん、太田孝司さん、落合保治さん、
古谷竹三さん、成井鼎さん、故石井一作さん、鈴木直さん、
高橋重二さん、故北島良平さん、渡辺郁兵さん、山田温恭さん。
************************************************
対象・人員・期間・回数は18歳以上の男子で1回あたり30名、
10日間、4月から11月のおおむね月2回、実質的な初年度の
昭和13年には年12回実施されています(資料(6))。
日々のスケジュールは資料(1)(5)(6)で内容が少しずつ違います。
季節や対象者によって変えていたのかも知れません。(5)(6)によれば
初日は13時集合、最終日は正午解散でともに作業はありません。
以下、T氏(仮名)が報国寮に参加したつもりごっこをするそうです:
(資料(6)賛与利)
これを見ていなかったおかげで
秦野寺山の里山巡りを楽しめた、
とT氏は申します。
しかしこの図では蓑毛と宮ヶ瀬の
間の、たぶん丹澤林道沿いに
あるっぽい、ということぐらいしか
わかりませんねえ。
丹澤報國寮への道
丹澤報國寮開所の昭和12年10月当時、既に蓑毛から宮ヶ瀬の丹沢林道が
開通済みです(昭和10年)。ただし山腹の道ですから崩壊しまくりだった
と思われます。アテにはできません。
当時の観光案内「丹沢山塊」(秦野山岳会編、資料(7))を見ると既に
バス路線もあり、
************************************************
・大秦野から蓑毛まで25銭、ヤビツ峠まで60銭(往復1円)
・大秦野から札掛までハイヤーで4円
・橋本から鳥屋まで60銭
・山北から神縄まで49銭
・伊勢原から大山まで35銭
・厚木から煤ヶ谷まで50銭、宮ヶ瀬まで90銭
************************************************
となっています。
1円=今の5,000円で換算するとかなり高いです。
秦野自動車(株)の
バスと社員。
(資料(8))
高いけど、
ガイドさん付きなら
乗りますか(笑)
バスも高いですが汽車も高いです。
************************************************
小田急で新宿から厚木まで86銭、大秦野まで1円16銭、渋沢1円23銭。
国鉄だと東京から平塚まで1円、山北まで1円44銭。
************************************************
報国寮開所の3ヶ月前には小田急がこんなことになってます↓
(小田急鉄道の破損)
(資料(5))
酒匂川に限らず本邦の
平野は概して河川の
後背湿地ですから、
日本中至る所こんな感じ。
寮費は県の負担ですが旅費については明記がないので自腹かも。
元気があれば大秦野から半日歩きもアリ、V派的には煤ヶ谷~
物見峠~黒岩~一ノ沢考証林~札掛も考えられますが、昼の集合
遅刻厳禁を考えるとリスキーです。
とすると大秦野から蓑毛までバスで、そこから柏木林道、ヤビツ峠
経由が無難っぽいです。
携帯すべき品として入団者心得((5)(6))に
************************************************
作業服(手袋、地下足袋、巻ゲートルを含む)、寝巻、腹巻、手拭、
石鹸、歯磨、弁当箱、印、雑記帳、鉛筆、鼻紙等
************************************************
とあります。弁当箱はカラではなく初日の昼食は途中のどこかで
各自適宜に取るらしいです。褌を忘れても何とかなったと思われ
ますが酒・煙草・夜食を忘れると悲惨です。
厚木市インターネット博物館の「丹澤報國寮絵葉書」によりますと
現地の全景はこんな感じ↓
(厚木市郷土資料館の
許可を得て転載)
http://ddbsvr.city.atsugi.kanagawa.jp/museum/post2/L00081.jpg
右上の全景写真は藤熊川を渡った対面の木に登って撮ったっぽいです。
後の建物は高松宮家「有栖川宮記念厚生資金」の援助による講堂で、
開所当時にはまだなかったそうです(4)。
左下は塩水隧道付近のヘアピン付近と思われます。現在は木が茂って
おり、このような展望は得られないそうです。
左上「魂」の「木暮書」は第2代林務課長木暮藤一郎氏と思われます。
木暮氏は「神奈川県林業史」(1)に多くの方々の回想があり、大変な
ヤリ手であって、(予算が潤沢な?)神奈川県の林務課長に東京府
から転ずるためにいろいろ運動したとか他人のアイディアをパクって
特許を取ったとか晩年はよくなかったとか、いろいろ書かれています。
ハンス・シュトルテさんによれば(9)、丹沢林道を諸戸の事務所から
札掛あたりに続く橋に
(林務課に常世正俊さんという方が
おられたようです)
と風流な名前をつけたのは、この木暮氏だったそうです。
また大洞隧道と塩水隧道の出入口にも「木暮書」があったそうですが、
大洞は再建され塩水は表札が落ちていて確認できなかった、とT氏は
申します。
T氏は厨房時代にバレーボール部にいたが、靴とかに「魂」と書き
入れることを強制され、アホらしくなってやめたそうです。以来
「魂」と書くヤツにロクなのはいないと確信しているそうです(笑)
(つづく)
【参考資料】
(1)宮澤敏雄「報国寮の回想」「造林史について想う」
神奈川県農政部林務課編「神奈川県林業史」昭和46年(1976)所収
http://www.e-tanzawa.jp/support/e-tanzawa_Supt/info/tanzawa-DB/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%9E%97%E6%A5%AD%E5%8F%B2/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%9E%97%E6%A5%AD%E5%8F%B209.pdf
pp.162~172
(2)神奈川県農政部林務課編「神奈川の林政史」 昭和60年(1985)
第13章「林業教育」
(3)和田正洲「丹沢報國寮」(「にのみやの歴史」第2号(1990.3))
(4)矢野慎一「戦時下・神奈川における報国寮の研究」
(「昭和のくらし研究」No.5(2007.3.))
(5)「丹澤報國寮勤労奉仕施設」(小冊子)昭和十三年三月 神奈川縣
(6)神奈川縣公報 第千百三十四号 昭和十二年九月三日
(7)秦野市史 第5巻「近代資料2」(昭和61年) p.179
(8)「図説秦野の歴史1995」(秦野市発行、1996)
(9)ハンス・シュトルテ「丹沢夜話」(1983)有隣堂
PR
この記事にコメントする
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
最新CM
[09/02 TI-AEK25]
[09/02 M氏]
[07/25 TI-AEK25]
[07/25 EA]
[07/03 TI-AEK25]
[07/03 shiro]
[03/30 EA]
[03/30 TI-AEK25]
[03/30 EA]
[06/20 TI-AEK26]
最新記事
(03/14)
(09/10)
(09/09)
(09/01)
(08/19)
(08/17)
(08/06)
(08/03)
(07/21)
(07/15)
最新TB
ブログ内検索
